
|
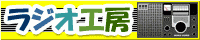
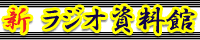
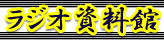
掲示板利用上 のお願い
投稿は実名(漢字かコールサイン)でお願いします
ハンドルネー ムでの書き込み、ラジオに無関係な宣伝や不穏当な書き込みは削除します
修理依頼は掲示板に書き込まないでください、ラジオ修理工房をご覧ください
ラジオ工房内サイト
ラジオ工房 ラジオ工房資料室
売店 真空管ラジオ回路図集
中津市の歴史と観光:城下町中津
管理人へのメール
アマゾン真空管式スーパーラジオ徹底ガイド(拙著)
4728487
ラジオ工房掲示板

|
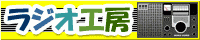
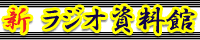
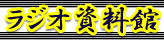
ラジオ工房内サイト
ラジオ工房 ラジオ工房資料室
売店 真空管ラジオ回路図集
中津市の歴史と観光:城下町中津
管理人へのメール
アマゾン真空管式スーパーラジオ徹底ガイド(拙著)
